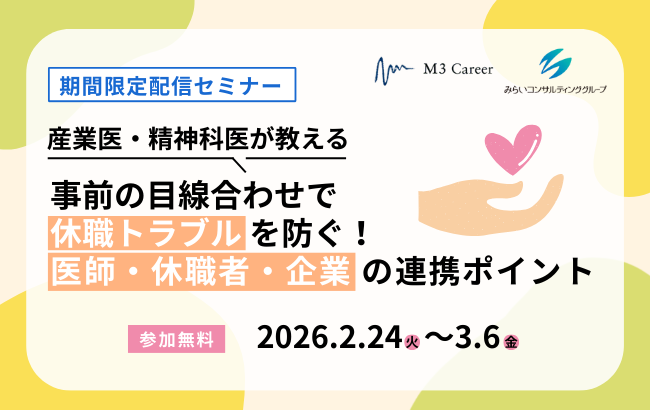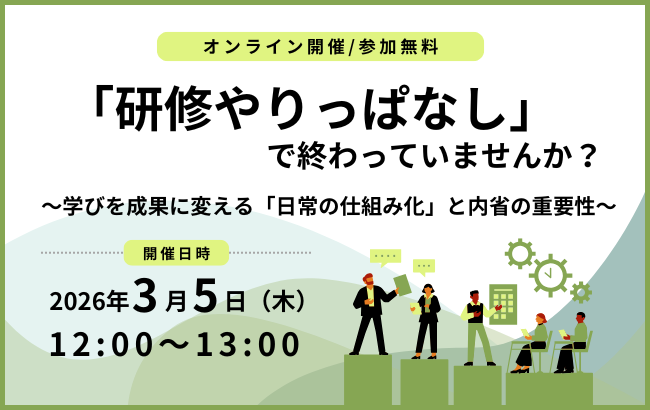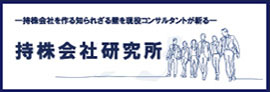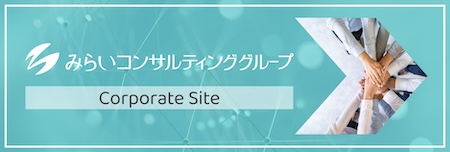投資をする人、しない人の違いとは?

「貯蓄から投資へ」というスローガンが政府から打ち出されてから、およそ20年が経ちました。この間に「iDeCo(イデコ)」や「つみたてNISA」といった少額から将来の資産形成を始められる制度が次々と導入され、「これくらいの金額からであれば投資を始めてみよう」という人も増えてきたと思います。NISA制度が始まってから証券口座を開設した人の約30%が投資未経験であった、というデータからも、一定の投資促進効果があったことがわかります。
しかし、日本ではいまだに資産の保有先を預金に頼る傾向があり、まだまだ投資へのシフトが進んでいない状況です。日本銀行が2022年8月に公表したデータをもとに日米の家計の金融資産構成を比較すると、日本は「預貯金」が54.3%を占める一方、「株式等」10.2%、「投資信託」4.5%と「預貯金」に大きく偏っています。一方、米国は「預貯金」が13.7%に対し、「株式等」が39.8%、「投資信託」が12.6%を占め、対照的な結果となっています。
では、なぜ日本は「投資に消極的な人」が多いのでしょうか。
一般的には、保守的な国民性やこれまで金融教育が重視されてこなかったという理由があげられています。ただ、長い歴史でみると60〜70年ほど前は家計資産の30%近くが株式等のリスク資産で運用されていたともいわれていますので、「日本人は安全志向で保守的であるから」ということだけでは、投資へのシフトが進まない理由とはいえないのではないでしょうか。
では、投資をしている人にはどんな人が多いのでしょうか。
投資に興味を持つきっかけは人それぞれです。老後資金のため、預金金利が低いから、などの理由が多いようですが、意外と「家族が投資をしているから」「友人や同僚に勧められたから」という方も多いのではないでしょうか。投資は難しくてよくわからない、リスクが怖い、と思っていた人でも、身近な人が投資をしていると聞くと一気にハードルが下がるものです。
また、昨今ではYouTubeなどの動画サイトやSNSの普及により「有名人が紹介していたから」「偶然耳にしたから」という理由で投資に興味を持つということも増えてきています。
投資をする人、しない人の違いは、個々人の性格や考え方の違い、知識の有無などももちろんありますが、それ以上に、知っている人がやっている、知っている人から紹介された、など、投資を「身近」に感じることができるかどうかが大きく影響している、といってもいいのではないでしょうか。
2022年12月16日に発表された税制改正大綱で、2024年からNISA制度が大幅に拡充される方向でまとまり、大きな話題をよんでいます。新NISA制度では、非課税可能期間が無期限化されること、非課税限度額が1,800万円に拡大されることなど、今まで以上に将来を見据えた資産形成がおこないやすくなります。
NISA制度の拡充をきっかけに周囲で投資を始める人が増えることが予想されます。昨今の物価上昇、社会保険料や税金の増加などで、預金が実質的に目減りするリスクに備え、「投資で資産をふやす」というのは大事な考え方ですので、まずは周りの人、知人がどうしているか、というのを聞いてみてはいかがでしょうか。そして、少額からでも資産形成のための投資を始めてみることをおススメします。
【関連記事】
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。