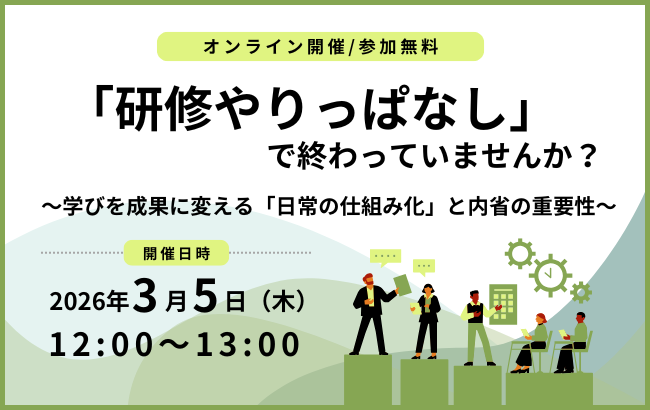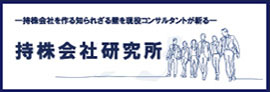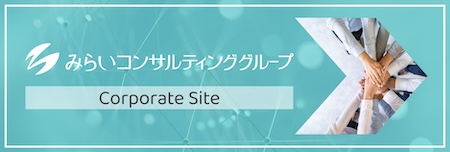【深圳レポート】第130回広州交易会がオフライン・オンライン同時開催

※本記事は、深圳イノベーションセンター(MICS)
広州交易会とは、中国広州で毎年春(4月)と秋(10月)の2回開催される貿易展示会であり、中国輸出入商品交易会(CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR)が正式名称である。
1回目が1957年に開催されていて、中国でもっとも歴史が長く、規模が大きい貿易展示会で、世界各地からバイヤー達が集まり、海外からの出展数も多いため、国際的にも影響力がある貿易イベントである。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、2020年春の第127回、秋の第128回、2021年春の第129回はオンラインで開催された。 2021年10月15日から開催されている第130回は、初めてオンラインとオフラインが融合したかたちでの試みとなる。ちなみに、オフラインで展示会が開催された第126回の時点で、広州交易会の累計輸出取引額は約14,126億米ドルに達し、約899万人の海外バイヤー達が出席したという統計になっている。
現在、広州交易会の各セッションの展示場の規模は118万5千㎡(東京ドーム25個相当)であり、国内外から26,000の出展者があり、210の国と地域から約20万人のバイヤーが出席することになっている。
中国国内にいる人がオフライン会場に入るには、新型コロナのワクチン証明以外に、48時間以内のPCR検査証明も必要である。なお、海外から渡航者については、中国に入ってから21日間の隔離を必要としている。
今年のオフライン展示エリアは40万平米(東京ドーム約9個分)で、16の商品カテゴリーに応じて51の展示エリアを設置し、合計19,181のブースと7,795社の企業が出店している。 オフラインの国際輸入セッションには、ヨーロッパ、米国、カナダを含む15の国と地域から、フォーチュン500企業や業界をリードする大手企業グループなど92社がオフラインで展示ブースを出している。
なお、オンラインの場合、既存の約60,000の出展枠には変わりはなく、実際に約26,000の中国国内および国外企業が出展することになる。現在、オンラインで出展された商品は282万個を超えて、過去最高記録を更新しており、そのうち88万個は新製品として表記されている。
グローバル取引において、国々の輸出入がまだコロナ前の状況に戻っていないなか、中国は積極的に内需拡大を狙っている。 その証とも言えるのが、今回史上初となる「農村活性化」のテーマである。中央政府による貧困緩和と農村振興の政策のもと、今年の広州交易会のオフライン展示会では、「農村振興特産品展示エリア」を設置し、出展費用を無料としている。
オンラインでも、貧困地域の企業が積極的な出展することを奨励するために、出展条件、出展企業数の数を制限しないなど企業の負担を軽減するための実践的な措置を取っていている。
また、進化を続けているオンライン形式であるが、バーチャルで会場を見せることで、より身近で臨場感を感じることができている。バーチャルブースではマウスを上下左右に動かすことで、展示場を歩き回っているような雰囲気を味わえる。
中国国内にいるバイヤー達は、オフライン会場に足を運ぶことができたので、今回のオンライン会場は主に海外のバイヤー向けになっているようで、これまでは中国語と外国語での対応となっていたのが、英語中心になっているブースが多いように感じる。
現在、世界的にコンテナ不足などによる海上運賃が高騰していることは中国だけの難題ではない。今回の広州交易会でオーダーが取れても、コンテナが予約できない、運賃が高くなり輸出価額に影響を与えるようなことが頻繁に起きているようだ。このような課題に直面して、例えば、サーバーラックの輸出業者はバイヤーと協議して、組立完了の製品ならコンテナに36個を詰めることができるが、ばらして詰めることで、124個を積むことができるような形式に変更するなどの工夫をすることで、両者に最適な取引方法を考案する事例も数多く紹介している。なお、現地での組み立て方法などについてはマニュアル動画を提供するなどして対応しているそうだ。
さて、「日本」というキーワードで検索してみたら、なんと7,788個の商品がヒットしている。日本と中国との自由な往来にはまだ時間がかかりそうだが、今回の広州交易会の規模からすると、商売には国境がないと実感している。 オンラインとはいえ自社商品・製品を中国やその他の国へ販売しようという意欲は高く、新たな日本ブランドが中国を席巻する日を楽しみにしている。
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。