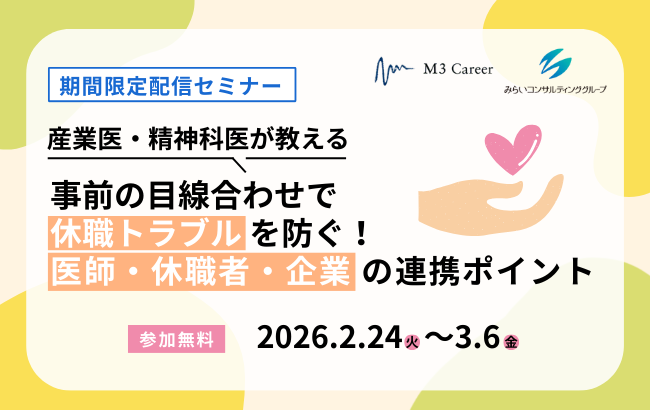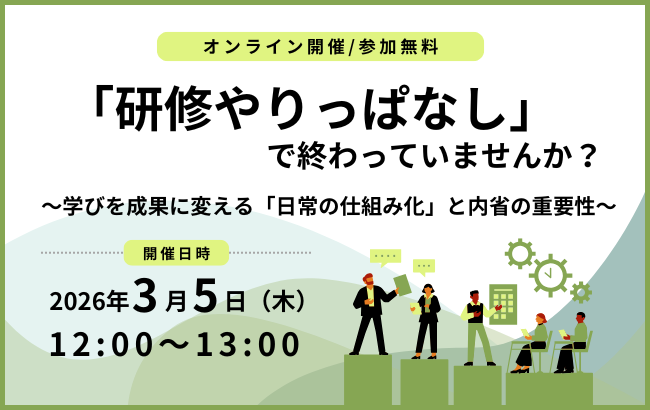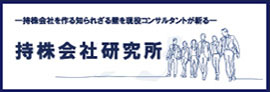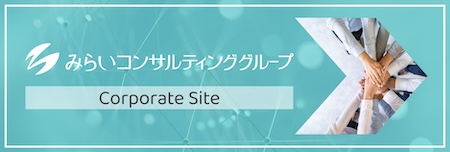2023年10月よりスタート インボイス制度
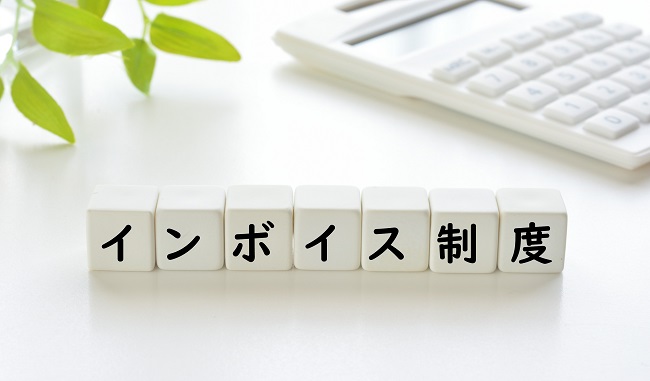
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される消費税に関する新しい制度です。最近はテレビコマーシャルなどでもさかんに言われていますので認知は高まっているようですが、もう準備はお済みでしょうか。いよいよ半年後に迫った制度について、あらためて制度趣旨と事前準備についてお伝えします。
① 制度趣旨 ~ なぜ始まるのか?
ざっくり言うと「消費税の適正な仕入税額控除を行うための新たなルール」です。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
(国税庁HPより引用)
この制度を導入する大きな目的は以下の2点です。
1 消費税の金額・適用税率を正しく相手に伝えることで、納税額の計算を正しくおこないたい
現在、適用される可能性がある消費税率は、10%、軽減8%、旧8%、旧5%の4種類が存在します。インボイスにおいては、これらを明確に区別して記載する必要があります。
2 益税を解消して不公平感をなくしたい
益税の解消とは、消費税相当額を買い手に請求しているものの消費税を納める必要の無い「免税事業者」の売上については、その売上に係る消費税分は国へ納められず、免税事業者の利益となっている現象を指しており、国はそれを問題視しているのです。
インボイスを発行しようとする事業者は、事前に税務署へ届出をし、かつ消費税を納める必要があります。納税と手間というダブルの負担が発生するため、同制度の中止を求める18万人以上の署名がフリーランスの方を中心に集まったというニュースを覚えている方もいらっしゃるかと思います。
②事前準備 ~なにをしたらいいか?
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(国税庁HPより引用)
上記のように「簡単に」記載されていますが、もちろん、一筋縄ではいきません。
売り手側としては、請求書作成システム・ソフトの更新が必要になりますし、請求書のみの話で終わらせるのではなく、バックオフィス業務全体の改革の契機としたい、DX化を進めたい、という経営者の意向で通常業務に加えた作業が発生している方もいらっしゃいます。
買い手(仕入)側の準備は、自社側でコントロールができないケースがほとんどですのでより注意が必要です。たとえば、免税事業者(これまで小規模で消費税納付が免除されていた事業者)との取引では、売り手がインボイス発行事業者にならなければ、売り手から請求された消費税分を買い手としては税額控除することができず、実質的に仕入額が増えることになるなど、損益インパクトも発生する可能性があります。そのような場合は、個別に価格交渉をするしかありませんので、早めの事前準備がとても大切になります。
実際に、各社ごとに異なる実務目線での懸念点は数多く考えられます。みらいコンサルティングでは部分最適ではなく、全体最適の目線でご提案することが可能です。少しでもお悩みのことがございましたら、お気軽に担当のコンサルタントに一声かけていただけますと幸いです。
【関連記事】
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。