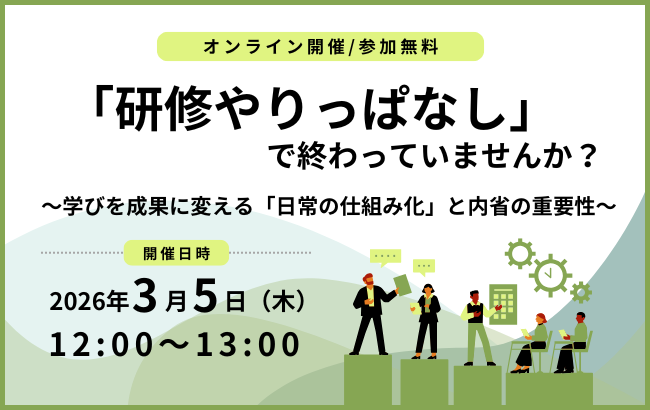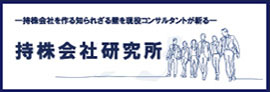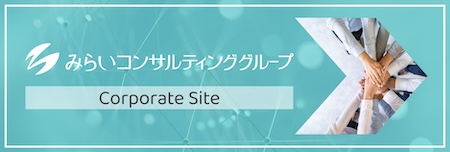「育成疲れ」の処方箋 ~社員が自ら育つ組織の作り方~

「社員が思ったように成長しない」。地方の中小企業の経営者からよく聞かれる言葉です。優秀な人材は首都圏に流出し、やっと採用できた社員の育成に必死で取り組んでいるにもかかわらず、なかなか成果が出ない状況、この「育成疲れ」は、会社の成長を真剣に考える経営者ほど深刻な悩みとなっています。採用市場では他社との競争が厳しく、入社してくる社員のビジネススキルも、必要な水準に十分に達しているとはいえません。それでも地域の経済と雇用を支える立場として、人材を育て、事業を発展させていかなければなりません。
「育成疲れ」の3つの特徴
この「育成疲れ」には、主に3つの特徴があります。
1.管理職が「答えを教えすぎる」傾向
ハラスメントを過度に意識するあまり若手への指導が及び腰になり、また成果を早く出そうとするあまり答えを先回りして教えてしまうため、社員の自律性や成長機会が失われています。その結果、若手社員は失敗を恐れ、自ら考えることなく上司に答えを求める傾向が強まっています。かつての「失敗から学ぶ」という貴重な経験が、現在は著しく不足しているのです。
2.管理職自身の「育てられた」経験の不足
多くの管理職は丁寧な指導を受けず、先輩の背中を見て育ってきました。実務能力の高さを買われて登用されましたが、「人の育て方」について体系的に学ぶ機会がないままでした。「自分も教えられずに育った」「仕事は見て盗むものだ」という考えが根強い一方、今の若手社員は丁寧な指導を求めています。この認識のギャップにより、経営者が期待する「次世代を育成する」という重要な役割が十分に果たされていない状況が生まれています。
3.研修効果の持続性の問題
外部研修への派遣などに相当の投資をおこなっているものの、その効果は一時的なものに留まっています。研修直後は参加者の意識は高まりますが、それを維持し実務に活かす仕組みが不足しているため、投じた教育コストに見合う成果が得られていない状況が続いています。
管理職の意識改革と仕組みづくり
人口減少に伴う労働人口の減少が深刻化する中、これらの「育成疲れ」の解消は企業の重要な経営課題となっています。一朝一夕の解決はむずかしくとも、着実に改善へとつなげていく施策があります。
1.「心理的安全性」の確保
かつての「失敗から学ぶ文化」を、意図的に組織全体に広げていく仕組みを作ることが重要です。特に管理職には、まず部下の話に耳を傾け、その努力を認める意識・言葉遣いを身につけるような機会を作っていきます。小さなことですが、これの繰り返しにより、若手社員が萎縮せずにチャレンジできる環境を作り出していきます。
2.段階的な挑戦の機会づくり
社員の成功体験を小さなステップに分解して、着実にチャレンジさせていきます。最初は上司との共同作業などから始め、徐々に権限を委譲していきます。社員の成長には「自身のできないことに気付く」機会が重要です。そのためにも、若手が小さな挑戦と失敗を繰り返す機会を、率先して作っていくことが不可欠です。地道ではありますが、一歩ずつ前進できる方法です。
3.管理職の育成力向上
研修効果を一過性のものとしないためにも、OJTの質を高め、日常業務の中で育成の機会に活かすことが重要です。たとえば、「ティーチング」と「コーチング」を使い分け、具体的なフィードバックや考えさせる質問の意識・スキルを研修で取り扱い、日々の業務で実践するだけでも、部下の成長を促すことにつながります。また、実践した内容を、定期的な育成会議の開催を通じて、管理職同士で共有することも効果的です。他の管理職の取り組みを知り、それぞれの強みや改善点を明確化することで、育成の質を高めることができます。管理職の育成意欲を持続的に高めるきっかけとなり、結果的に組織全体の成長につながることが期待できます。
これらの取り組みを通じて、管理職は「プレイヤー」から「育成者」へと意識が変わっていきます。最初は戸惑いがあっても、経営者の期待する「人を育てる」役割を、管理職一人ひとりが実践できる仕組みを整備していくことで変化を生みだしていきます。
地方の中小企業こそ、「人を育てる力」がこれからの競争力の源泉になっていきます。「人を大切にする」ということは決して甘やかすことではなく、組織の育成力を具現化していくことです。社員一人ひとりが自ら成長する組織づくりにご興味のある方は、ぜひ一度みらいコンサルティンググループの担当者にご相談ください。
【関連記事】
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。