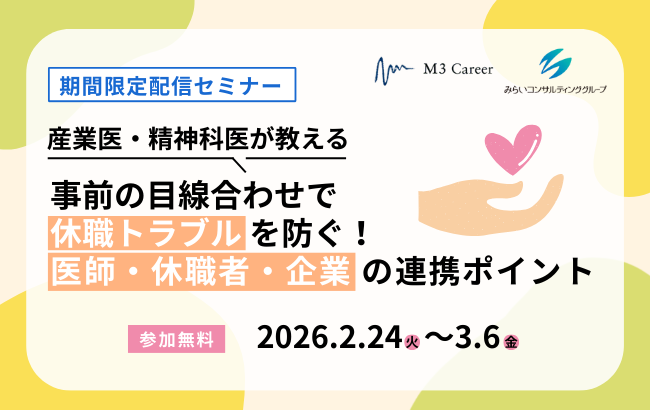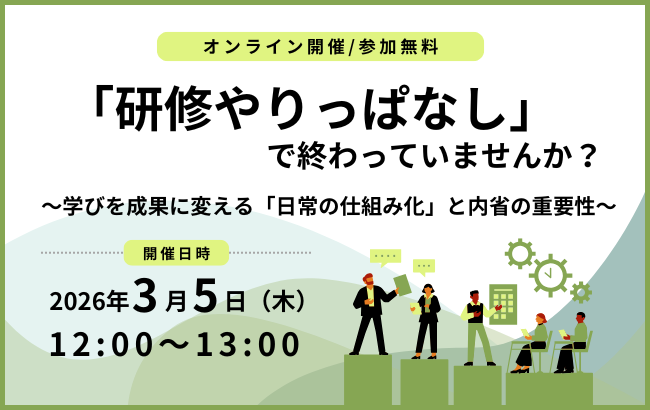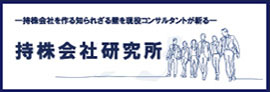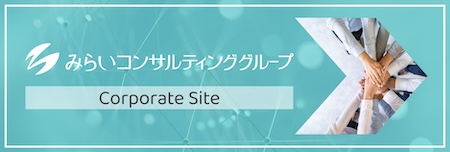なぜ、私たちは「LeRIRO福岡」を応援するのか?(シリーズ第2回)はじめは「視界不良」

前回、私たちがルリーロ福岡とどのように出会い、共感の輪が広がっていったのかをお話ししました。今回は、その共感から具体的な支援へと踏み出した私たちに立ちはだかった、最初の「視界不良」についてお伝えしたいと思います。
デュアルキャリアへの挑戦
ルリーロ福岡のユニークな点は、選手たちがラグビー選手であると同時に、地域の企業で働く社員でもあるという「デュアルキャリア」モデルにあります。私たちはこのモデルを持続可能なものにするためには、選手たちがただ雇用されるだけでなく、企業の一員としても活躍していることが不可欠だと考えました。この仮説のもと、私たちはみらいコンサルティンググループで培ってきた独自の週報システム「ココロの共有」を、ルリーロの若手メンバーの一部に導入することにしました。「ココロの共有」は、単なる業務報告書ではありません。仕事を通じて感じたことや気づき、時には悩みを上司にシェアし、対話を通じて内省を深め、成長を促すためのツールです。私たちはこれを活用することで、選手たちがビジネスパーソンとしての意識を高め、仕事とラグビーの「二刀流」を両立できるような支援ができるはずだと考えました。
厳しい現実と「気持ち」の壁
取り組みのスタートにあたり、まず私たちは対象となる若手メンバーに、スポーツ選手とビジネスパーソンというデュアルキャリアの意識を高めるための研修を実施しました。そして、いよいよ毎週の週報提出が始まりました。
しかし、現実は私たちが考えていたほど簡単なものではありませんでした。おりしも、ラグビーの公式戦シーズンが始まった時期と重なったこともあり、なかなか提出いただけない週が続いたのです。
ルリーロ福岡は、リーグワン(Division3)への参戦初年度。ラグビーの戦果としても厳しい状況が続いていました。グラウンドでの厳しい戦いに加え、慣れない仕事、そして週報の提出。選手たちの負担は想像以上に大きかったのかもしれません。
このまま続けていても、本当に選手たちの役に立てるのだろうか?私たちの支援は、かえって彼らにプレッシャーを与えているだけではないのか?そんな自問自答を繰り返す、そんな「視界不良」の半年間でした。
成果と「気持ち」の相関関係
「スポーツとビジネスの両立」「デュアルキャリア」などと、言葉にすると非常に響きがよく、簡単に聞こえます。しかし、実際にその道を歩む選手たち、そしてそれを支える企業にとっては、決して甘いものではありません。
プロスポーツである以上、ラグビーでの成果は非常に重要です。そこで結果が出ないことは、選手本人やチームだけでなく、応援しているスポンサー企業にも、そしてルリーロの場合は地域にも、決して良い影響を与えません。ビジネスの世界でも同じです。企業でのパフォーマンスが上がらなければ、その選手の価値を社内で認めてもらうことは難しくなります。
私たちはコンサルタントとして、とかく「あるべき論」をお伝えする立場にあります。目標を設定し、計画を立て、それを実行に移す。それが最も効率的で成果に繋がる道だと提案します。しかし、この半年間で私たちが痛感したのは、現実的な壁の多くが、時間の制約や物理的なものではなく、「気持ち」の問題に起因しているということです。
スポーツで結果が出ない時は、練習に集中したいという気持ちが強くなるでしょう。慣れない仕事でうまくいかない時は、仕事に気持ちが向かなくなるかもしれません。デュアルキャリアの成功には、この「気持ち」のコントロールと、それを支える周囲の理解と働きかけが不可欠だと強く感じました。
この「視界不良」の時期を経て、私たちはルリーロ福岡への支援のあり方をもう一度深く考えることになります。それは、単に仕組みを提供するだけでなく、選手の「気持ち」に寄り添うことの重要性を私たち自身が学ぶ、貴重な経験となったのです。
【シリーズ記事】
なぜ、私たちは「LeRIRO福岡」を応援するのか?(シリーズ第1回)
共感の出会い(セレンディピティ)
「人が育つ」組織を育てる人事評価・育成システム 「MIRAIC」
独自の週報システム「ココロの共有」