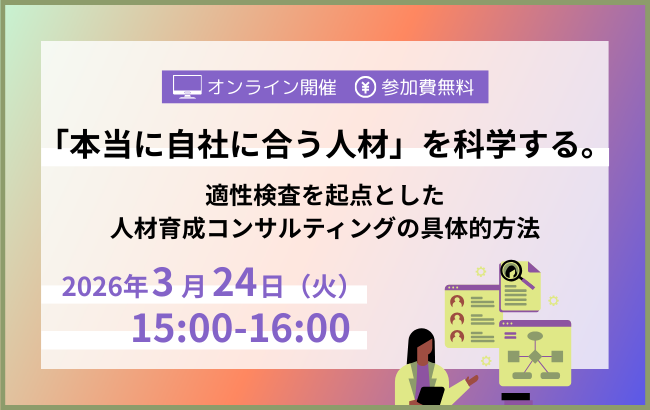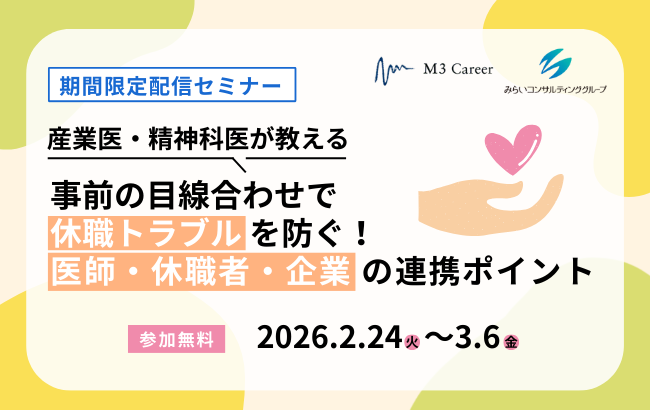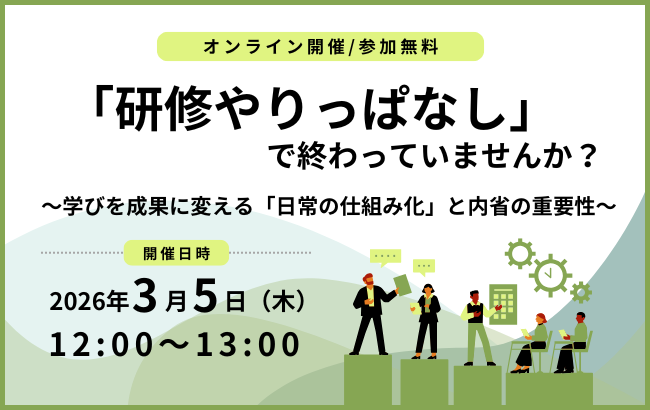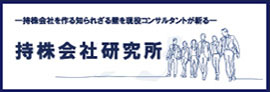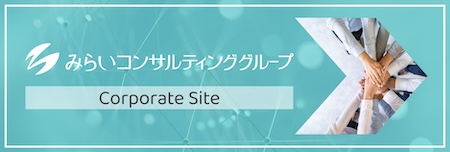価格転嫁を「準備」と「対話」で乗り越える!

原材料費やエネルギー価格の高騰が続くなか、多くの中小企業が頭を悩ませているのが「価格転嫁(値上げ)」の問題ではないでしょうか。
中小企業庁が2025年3月に実施した調査によると、原価上昇分の一部でも価格転嫁を実現できた企業は「52.4%」。つまり、約半数の企業は、コスト増を自社で被っているという厳しい現実があります。
同じような経営環境にありながら、価格転嫁できた企業と、そうでない企業。 この両者を分けたものは何だったのでしょうか?
その根本的な違いに目を向けることこそが、これから値上げに踏み出そうとする企業にとって、最大のヒントになります。 また、来年1月には「改正下請法(中小受託取引適正化法)」の施行も控えています。取引条件の透明性が高まるこの「追い風」を活かすためにも、今こそ自社の取り組みを見直す絶好のタイミングです。
価格転嫁を成功させるために不可欠な「3つの準備」と、交渉時の心構え。その具体的なポイントをみていきましょう。
成否を分けるのは、景気ではなく「自社の準備」
調査結果から見えてくるのは、価格転嫁の成否を左右するのは、景気や業界動向といった「外部要因」以上に、「自社の準備状況」が大きく影響しているという事実です。 具体的に、どのような準備が必要なのでしょうか。
1. 自社の価値を「言語化」して整理する
価格転嫁が進んだ企業には、自社の「強み」を明確に整理し、取引先に伝わる言葉に変換できている傾向があります。 「品質」「技術力」「納期対応」「アフターサービス」。これらは、みなさまにとっては当たり前のことかもしれません。しかし、それを改めて「自社だからできること」「自社が選ばれている理由」として言語化し、説明できるかどうかが、交渉の土台となります。 これは交渉の武器になるだけでなく、自社の存在価値を社員と再認識するよい機会にもなります。
2. 原価を「数字」で見える化する
交渉で最も重要になるのは、値上げの根拠となる原価を「数字」で具体的に説明できるかどうかです。 「なんとなく苦しいから上げてほしい」では、相手も納得できません。「材料費が〇%、外注費が〇%上昇したため、トータルで〇円のコスト増になっている」と、事実(ファクト)に基づいて示すことで、取引先も状況を理解しやすくなります。 また、原価を見える化する過程は、社員の利益意識を高める効果もあります。実際に、幹部社員の会話が「売上高」から「粗利益」へと変化し、筋肉質な経営体質へ変わった会社を、数多く見てきました。
3. 価格だけでなく「コスト全体」から考える
価格転嫁は、単に「単価」を上げるだけが正解ではありません。 納期、発注単位(ロット)、仕様、配送頻度など、コスト構造に影響する要素は他にもあります。視野を広げて取引条件全体を見直すことで、「単価は据え置く代わりに、発注ロットを大きくして配送コストを下げる」といった、価格以外の着地点が見つかることもあります。 柔軟な発想を持つことで、交渉の幅は大きく広がります。
価格転嫁は「説得」ではなく「対話」する姿勢で
値上げの交渉は、誰にとっても気が重いものです。「長年の関係が悪化しないか」「取引を切られないか」という不安から、つい先送りにしてしまう気持ちもよく分かります。
しかし、値上げ交渉を「相手を説得して、承諾させる場」と捉えると、どうしても対立構造になりがちです。 そうではなく、「自社の状況を正しく伝え、今後もよりよい価値を提供し続けるための相談をする場」と捉え直してみてはいかがでしょうか。
自社の原価状況を数字で示し、提供している価値を伝え、どうすればお互いにメリットのある取引を継続できるか。 その「対話」を重ねるプロセスこそが、真のパートナーシップを築くきっかけになります。
制度的な「追い風」を活かし、準備から始めましょう
改正下請法という制度的な後押しもあり、価格転嫁を取り巻く環境は確実に変わりつつあります。 価格転嫁を単なる「値上げのお願い」ではなく、「取引先へよりよい価値を提供し続けるための、前向きな取り組み」と捉え直し、まずは自社でできる「準備」から始めてみてはいかがでしょうか。
みらいコンサルティンググループでは、自社の強みを再発見する「価値発掘プロジェクト®」や、交渉の根拠となる「原価管理」に関するご支援をおこなっています。 「何から手をつければいいかわからない」という場合も、ぜひお気軽にご相談ください。
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。