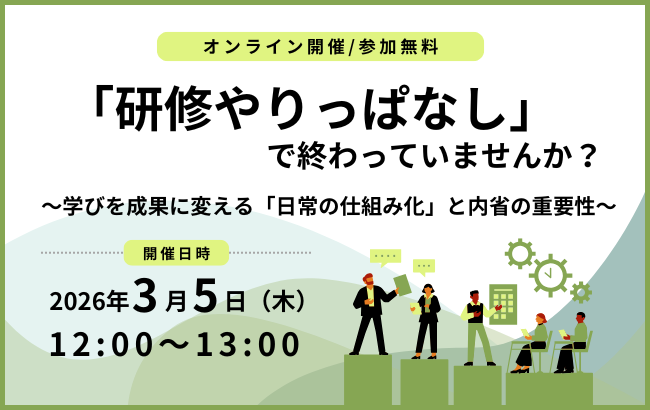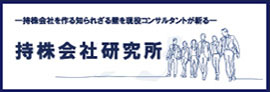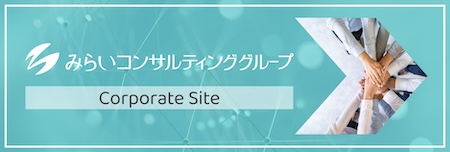「多様性」が企業を強くする:ダイバーシティ経営を進めるために必要なこと

近年、「ダイバーシティ経営」の推進がより強く求められるようになってきました。
ダイバーシティ経営とは、企業が多様な人材を積極的に受け入れ、その多様性を経営資源として活用する経営手法のことを指します。
具体的には、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向、宗教などの違いを持つ人々を組織に取り込み、その多様な視点や経験を活かしてイノベーションを促進し、競争力を高めることを目指します。
これらの対策が必要なのは上場会社、と思われがちですが、地域経済を支える中堅中小企業でも、この「ダイバーシティ経営」は避けて通れない課題となってきているのではないでしょうか。
なぜ、ダイバーシティ経営が必要か
背景には、以下のような要因があると考えます。
労働力の多様化
少子高齢化や労働力不足が進むなかで、企業は多様な人材を活用する必要があります。女性の社会進出や高齢者の再雇用、外国人労働者の受け入れなど、多様な人材を積極的に採用することは避けて通ることはできません。
グローバル化の進展
企業が国際市場で競争するためには、多様な文化や価値観を理解し、対応する能力が求められます。グローバルな視点を持った経営を推進するためには、多様なバックグラウンドを持つ人材の活用が有効です。
イノベーションの促進
多様な視点や経験を持つ人材が集まることで、新しいアイデアや発想が生まれやすくなる、というのはよく言われることです。VUCAの時代、革新的な製品やサービスを創出し、市場での競争力を高める一助になるのではないでしょうか。
ダイバーシティ経営を進めるためのポイント
一方で、「ダイバーシティ経営を進めようとしたが途中で頓挫してしまった…」というお客さまの声もよく伺います。
このような企業では、とにかく「制度」を整備するところから着手しようとしていたり、またいわゆるアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)をなくそうと研修等をくりかえしているケースがよく見受けられます。
制度構築や教育は確かに大事ですが、何十年もしみついてきた人の思考のクセは、そう簡単には直すことはできません。
本当にダイバーシティ経営を推進しようと思ったら、以下の3点が大切だと考えています。
①まず「やってみる」
「習うより慣れろ」といいますが、いろいろと制度を作るよりも、まず「やってみる」方が効果が大きいように思います。
当社でも、数年前より海外人材の採用を進めています。最初は、海外人材が日本で仕事ができるのか…と不安が先行していましたが、実際に入社してみるととてもやる気と能力に満ち溢れた人材で、日本人といっしょに、もしくはそれ以上に大活躍してくれています。
もちろんいいことばかりではなく、海外人材が働くうえではいろいろなハードルが出てきます。これに対しては、出てきた課題について社員間で話し合い、「より働きやすい環境を作ろう」と行動する雰囲気が生まれています。
頭で考えるばかりで動かないよりも、行動しながら考えていった方が、新しい仕組みは導入しやすくなる実例だと思います。
②「評価」しない
人の行動を良い・悪いと「評価」すると、それぞれの価値観によって見方が異なり、ダイバーシティ経営をさまたげる要因となります。まず、評価は一度横におき、実際におこっていることを「事実(誰が見ても同じこと)」ベースで認識することが大切です。そして、その事実を「違い」として認識することで、お互いの素晴らしい点をみとめ、さらに素晴らしくするためにはどうするか?と考える方向に社風を変えることができます。
③「言葉」を変える
社風が変わってきたら、元に戻らないよう定着させることが重要です。人間の脳は耳から入ってきた言葉をうけて考え、行動を起こします。そのため、行動そのものを無理に変えようとするよりも、日々使う「言葉」を変えることがとても効果的なのです。
言葉を変えることによって、新しい仕組みも「習慣化」しやすくなります。
ダイバーシティ経営に対して大上段に構えて取り組むよりも、日常のなかでできることから取り組んでいくことで、社風の変革は進みやすくなります。
みらいコンサルティンググループでは、自社での体験も含めダイバーシティ経営推進のご支援も多数おこなっていますので、お悩みがありましたらぜひご相談ください。
【関連記事】
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。