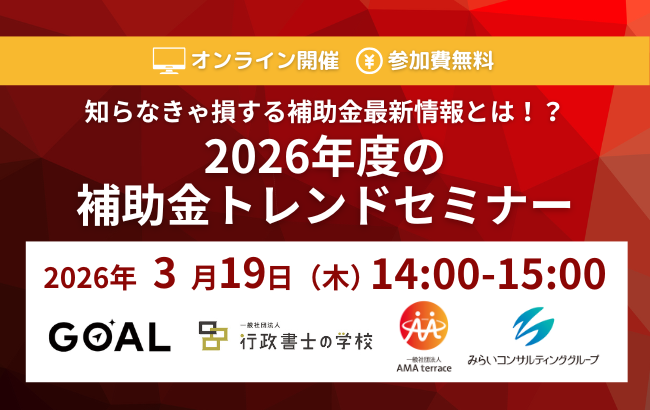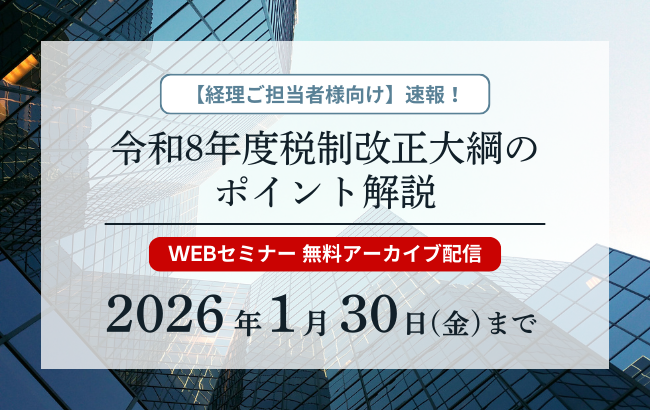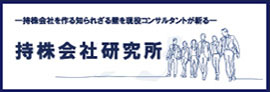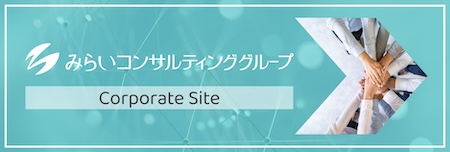高校野球に学ぶ、組織のなかでの「心の育て方」
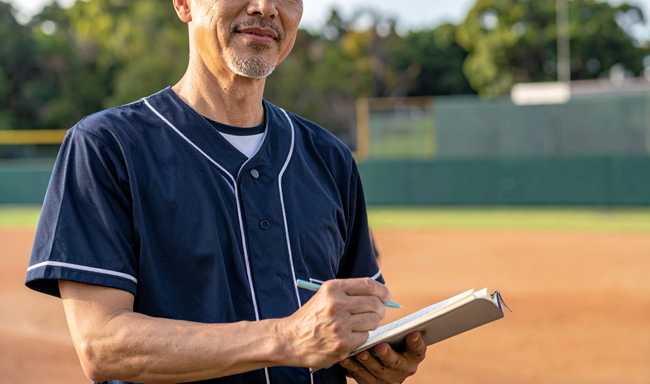
今年の夏の甲子園は、沖縄県代表・沖縄尚学高校の優勝で幕を閉じました。同校の強さの背景には、比嘉公也監督による「選手が自ら考え、行動することを重視する指導」があります。なかでも注目すべきは、監督と選手の間で交わされる「野球ノート」の取り組みです。
チーム崩壊の危機から生まれた「野球ノート」
比嘉監督が野球ノートを始めたきっかけは、監督就任わずか2か月後に発覚したチーム内の暴力事件でした。
「プレーの様子を見ているだけでは、選手の心や本当の気持ちはわからない」
そう痛感した監督は、選手の心に触れる方法を模索しました。
解決策としての「言葉の交換」
悩み抜いた末にたどり着いたのが、野球ノートです。ルールはシンプルですが徹底しています。
- 全員が1冊ずつノートを持つ
- 毎日感じたことを書き、監督と交換する
- 提出は必須。守れない場合はペナルティもある
こうして、監督と選手が毎日言葉を交わす環境が整いました。
実践がもたらした効果
新チーム発足後、比嘉監督は全員のノートを読み、一人ひとりに必ず手書きで返事を書きました。
ノートの目的は技術向上だけではありません。心や感性の成長です。比嘉監督はこう語ります。
「野球だけじゃだめなんです」
日常の小さな変化に気づく力を養うことで、人として成長し、結果的に野球の上達にもつながると考えています。
指導者自身の成長
野球ノートを続けるなかで、比嘉監督は選手の内面変化に気づけるようになっただけでなく、自身の言葉遣いや伝え方にも変化を感じたといいます。
つまり、この取り組みは選手だけでなく、指導者のコミュニケーション力を高める効果もあったのです。
ビジネスに応用できる「心の共有」
野球ノートのように、定期的に感情や振り返りを言語化し共有することは、組織にも大きな効果をもたらします。
- 自身の意見や失敗した経験を安心して発言できる雰囲気が生まれる
- 新しいアイデアや挑戦が出やすくなる
- 個人と組織の成果向上につながる
- 信頼関係が醸成され、エンゲージメントが高まる
自分の気持ちを書き出し、相手が理解して応答するプロセスが、「尊重されている」という実感を生み出すのです。
企業での活用例:MIRAICの「ココロの共有」
私たちみらいコンサルティンググループが提供する人事評価・育成システム「MIRAIC(ミライク)」には、「野球ノート」と似た仕組みとして「ココロの共有」があります。
「今週うまくいったことは?」「新しい気づきは?」「一週間を振り返ってどう感じた?」といった内省を促す問いに答える週報ツールです。社員は短いスパンで仕事を振り返り、気持ちや考えを言葉にすることで自己成長につなげます。
「ココロの共有」を導入したお客さま企業では、若手中途社員が「今週の社内実技試験は必ず成功させます」「入社して半年、充実した日々でした」といった意思や感情を表明。その結果、部長や社長は「メンバーの本音ややる気を知ることができ、関係性がよくなった」ことを実感していただいています。
皆さまの組織でも、気持ちや考えを言葉で交換するコミュニケーションを始めてみてはいかがでしょうか。高校野球の現場で効果が証明された「心の育て方」は、組織と個人の成長を同時に実現できるはずです。
「人が育つ」組織を育てる人事評価・育成システム
【関連記事】
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。