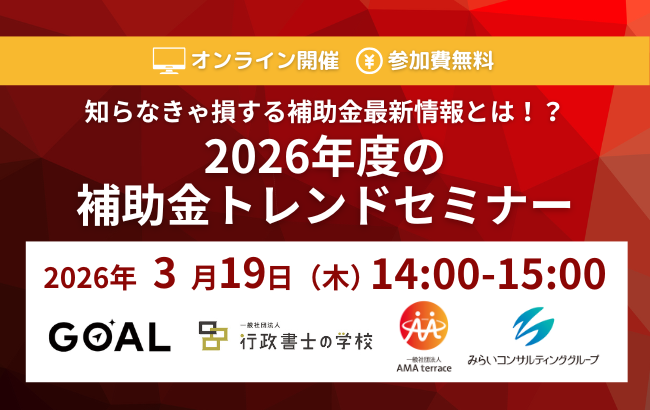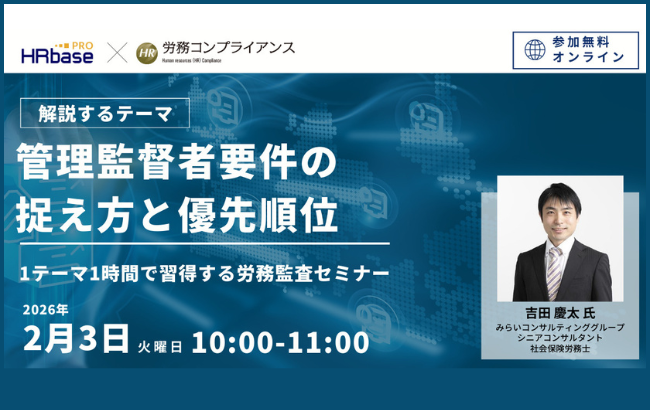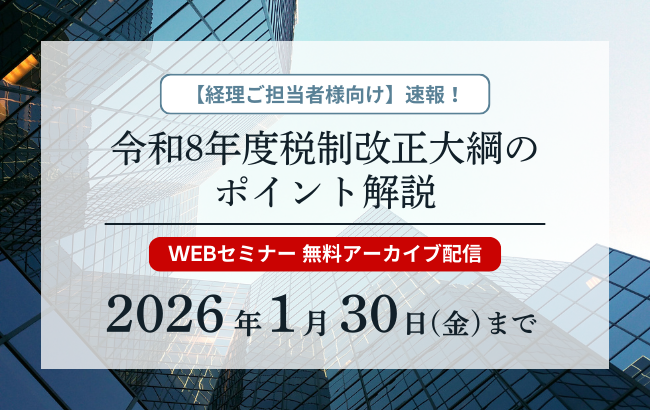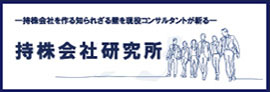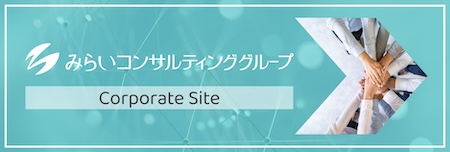AIは「不自然な経費」を見抜く。2026年から激変する税務調査、会社が備えるべきことは?

「うちの会社はちゃんと申告しているから大丈夫」…本当にそうでしょうか?
2026年、税務署に次世代の国税システム(通称:KSK2)が導入され、AI(人工知能)を活用した新しい税務調査が本格的に始まります。この変化は、経理の現場や会社の経営に大きな影響を与える可能性があります。
AIは、過去のデータや同業他社との比較から、人間では見つけにくい「不自然な数字の動き」を瞬時に見つけ出します。なぜ、あなたの会社はAIに目をつけられてしまうのか?そして、これからの税務調査にどう備えればよいのか?ポイントをわかりやすく解説します。
紙の書類も丸ごとデータ化。AIが税務署の“目”になる
今回の大きな変革の一つが、AI技術を使った文字読み取り機能(AI-OCR)の本格的な活用です。
現在、税務署に紙で提出された申告書は、一部の情報だけが人の手でシステムに入力されています。しかし2026年からは、所得税や法人税など、ほぼ全ての申告書(約2,300種類)が紙で提出されても、スキャナーとAI-OCRによって文字情報まで含めて丸ごとデータ化されます。
これにより、これまで十分に活用されてこなかった紙の書類の情報も、巨大なデータベースに集約されることになります。いわば、税務署が企業のあらゆる活動をデジタルデータとして見通せるようになる、ということです。この変化に伴い、申告書の様式もAIが読み取りやすいデザインに新しくなる予定です。
AIは“会社のクセ”を見抜く。税務調査はここまで変わる
集められた膨大なデータは、AIによって分析され、税務調査のあり方を根本から変えていきます。
これまで、法人税、所得税、相続税といった情報は、それぞれの税目の担当部署が個別に管理していました。しかしKSK2では、これらの情報が一つのデータベースで横断的に管理されるようになります。
たとえば、調査官は「A社の法人税申告」を見ながら、同時に「A社社長個人の所得税や相続税の申告状況」を瞬時に確認できるようになります。会社と個人の間のお金の不自然な動きなども、より簡単に見つけられるようになるのです。
さらに、AIは以下のような分析を得意とします。
- 過去のデータとの比較:「売上は横ばいなのに、今期だけ交際費が3倍に増えているのはなぜ?」
- 同業他社との比較:「同じ業種・規模の会社と比べて、この会社の原価率は異常に高いのはなぜ?」
- 取引の関連性分析:「この取引先は、本当に実態がある会社なのか?」
AIが「おや?」と疑問に思った点をリストアップし、調査官はその情報をもとに、より深く、鋭い調査を行えるようになります。これにより、不正が見込まれる納税者の抽出精度が格段に向上すると言われています。
「なんとなく」は通用しない。今すぐ会社が見直すべきこと
では、進化した税務調査に対応するために、企業は何を準備すればよいのでしょうか。重要なのは「経理の透明性」を高めることです。
(1)経理・申告業務のデジタル化と証拠の管理
- 日々の取引を正確に入力する: 会計ソフトなどを活用し、日々の取引をタイムリーかつ正確に入力しましょう。人的なミスを防ぎ、データの整合性を保つことが基本です。
- 電子帳簿保存法に対応する: メールで受け取った請求書などの電子データは、法律のルールに従って保存することが義務付けられています。データの改ざん防止も重要なポイントです。
- 証拠書類(エビデンス)を徹底的に残す: AIが疑問を持ちやすい変動の大きな経費や特殊な取引については、「なぜ、そうなったのか」を説明できる資料をセットで保管しましょう。たとえば、「高額なPCを購入した際の稟議書」や「接待相手や目的を記したメモ」などです。
(2)誰が見てもわかる、一貫性のある会計処理
AIは、過去のデータとの比較分析を得意とします。そのため、特別な理由なく会計処理のルールを毎年変えたり、勘定科目を頻繁に変更したりすると、「何かを隠そうとしているのでは?」とAIの注意を引く可能性があります。
会計処理には一貫性を持たせ、誰が見てもその会社のルールがわかる状態にしておくことが、あらぬ疑いを招かないための重要な守りとなります。
2026年から始まる税務調査のDXは、もはや他人事ではありません。AIによる分析が標準となる時代では、どんぶり勘定や「これくらい大丈夫だろう」という甘い見通しは通用しなくなります。
日々の経理業務をデジタル化し、取引の証拠をきちんと残し、一貫性のある会計処理を行うこと。こうした当たり前の取り組みが、結果的に会社の信頼を守ることにつながります。
もし、自社での対応に不安を感じたり、何から手をつければよいかわからなかったりする場合は、専門家の力を借りるのも一つの有効な手段です。
みらいコンサルティンググループでは、業種や業務フローに応じた経理業務の改善、クラウド会計の導入、電子帳簿保存法への対応支援など、企業のバックオフィス業務をトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。