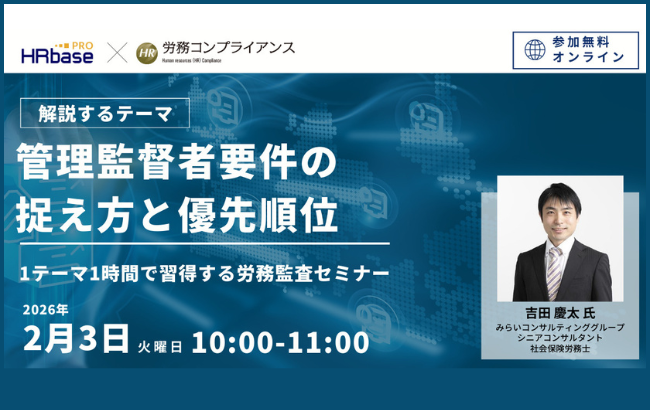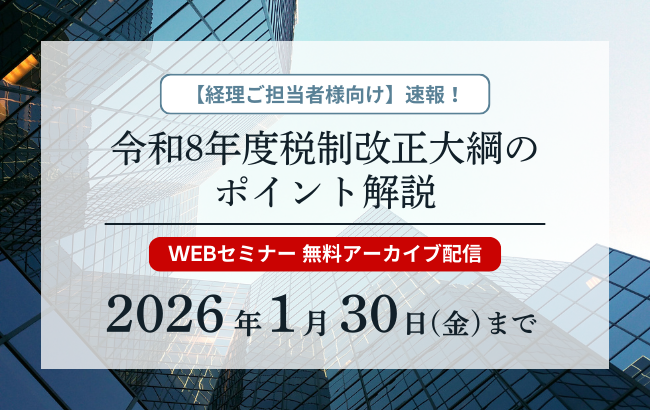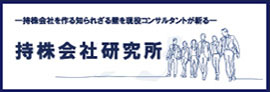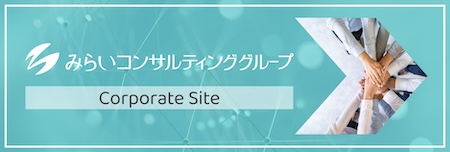「後継者探し」の常識が変わる?知っておきたい2つの最新動向

「社長の高齢化」と「後継者不足」。これは、今や日本経済全体の深刻な課題です。 中小企業白書(2025年版)によると、後継者が「未定」の企業は約53%と半数を超え、黒字でも廃業を選ぶ企業が後を絶ちません。
しかし、私たちが事業承継の現場でご支援をしていると、この課題を解決しようとする“2つの大きな流れ”が全国的に広がっていると感じます。 それは、「承継先の多様化」と「地域ぐるみの支援」です。今回は、会社の未来を考える経営者に知っておいていただきたい、この最新動向を見ていきましょう。
親族から“第三者”へ。加速する「M&A承継」という選択肢
かつて、事業承継といえば「親から子へ」が一般的でした。しかし、少子化や価値観の変化もあり、その常識は変わりつつあります。
その受け皿として急増しているのが、社外の経営者や買い手企業に未来を託す「第三者承継(M&A)」です。 「事業承継・引継ぎ支援センター」の発表でも、第三者承継の成約件数は2024年度に2,132件と、過去最高を更新し続けています。
この背景には、国も「第三者承継」を本気で後押しし始めたことがあります。 たとえば、「事業承継・M&A補助金」では、M&Aにかかる専門家費用だけでなく、承継後の会社の統合(PMI)や、新しい挑戦(第二創業)に必要な費用まで、幅広く支援対象となっています。
M&Aは、単に「会社を売る」ことではありません。よいパートナーと組むことで、会社がさらに成長するための「起爆剤」となり得るのです。
地域が「担い手」に。“自治体主導”の後継者マッチング
もう一つの大きな流れは、「地域ぐるみ」で後継者問題に取り組む動きです。その中心的な役割を担い始めているのが「自治体」です。 地域の有力企業が廃業すれば、雇用が失われ、地域経済そのものが衰退してしまう。この危機感が、自治体を「後継者探しの担い手」へと変えさせています。
たとえば、静岡県浜松市の「ツグはまコンシェルジュ」では、創業希望者と後継者不在の企業とを、市が丁寧にマッチングしています。 企業側は「親族」や「社内」以外の新たな選択肢を得られ、創業希望者側も、ゼロから立ち上げるリスクを抑えて事業を始められます。
こうした自治体によるマッチング支援は、熊本市、豊橋市など、全国の中核都市で急速に増えています。
「選択肢」と「支援先」の拡大をどう活かすか
この動向の中で、ぜひ押さえておいていただきたいポイントは、以下の2点です。
ポイント①:「想い」を継いでくれる相手を探す
承継先の選択肢が大きく広がった今、最も大切なのは「自社にとって最も魅力的な後継者は誰か」という視点を持つことです。 「子どもが継がないから」と諦める必要は、もはやありません。
そのためには、まず経営者自身が、自社の「理念」や「価値」、従業員や取引先への「想い」を整理し、言語化することが不可欠です。その「想い」に共感し、未来を築いてくれる相手を幅広く探すことが、成功のカギとなります。
ポイント②:「後継者探しの情報源」として外部機関を活用する
「想い」を共有できる相手を自社だけで探すのは困難です。そこで活用したいのが、「自治体」や日頃付き合いのある「地域金融機関」「商工会議所」です。
特に自治体は、移住希望者や創業希望者など、私たちが知らない幅広い情報ネットワークを持っています。 「後継者探しで迷ったら、まず地域の窓口に相談してみる」。その行動が、思わぬ出会いを生み出すかもしれません。
「会社の終わり」ではなく、「未来をつくるプロジェクト」へ
事業承継は、決して「会社の終わり」を意味するものではありません。 それは、大切に育ててきた事業や従業員、お客さまとの関係を、次の時代につないでいく「未来をつくるためのプロジェクト」です。
選択肢と支援先が広がっているからこそ、外部の力を上手に活用しながら、次の担い手との出会いを積極的に作っていくことが、これからの時代、ますます重要になっていきます。
少しでも気になることがございましたら、みらいコンサルティングの担当者までご相談いただけますと幸いです。
【関連記事】
サプライチェーン事業承継 ~貴社の取引先は事業承継の準備ができていますか?~
「事業承継」は地域の未来を共創すること
会社経営についてご相談ください
- 課題を明確にしたい。
- 課題解決の方法がしりたい。
- 課題の整理がしたい。
- セカンドオピニオンがほしい。
企業経営に関するプロフェッショナル集団が
お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。